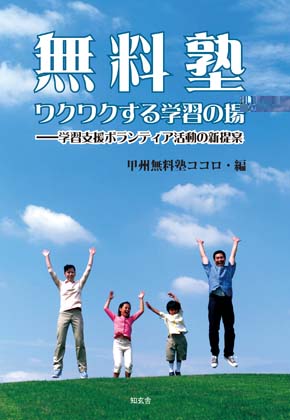●無料塾 ワクワクする学習の場
――学習支援ボランティア活動の新提案 (2019年9月新刊)
甲州無料塾ココロ(代表:西田隆男) 編著
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■電子書籍: \700 (消費税別)
2019年9月2日初版発行
■POD書籍 : \1,200 (消費税別)/(A5判128頁 ISBN978-4910056036)
2019年9月2日初版発行 →アマゾンでの購入はこちら
(ご購入はPOD書籍取扱い店:アマゾンでお求めください。★その他書店では取扱いがございません)
(購入はTOPページの電子書籍販売店でお求めください)
◎本書について
現代日本の教育の盲点を埋める学習支援ボランティア活動と新しい民間レベル教育のあり方を提案する書。
|
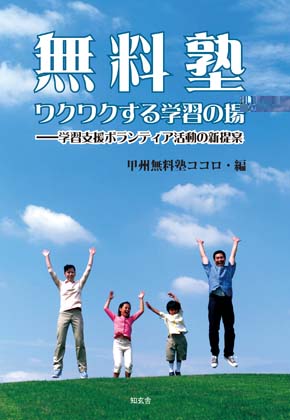
|
|
6人に1人が貧困状態に置かれている格差社会日本における子どもの教育現場で、公平な学習環境を提供するために活動する学習支援ボランティア「無料塾」による教育の新しいあり方を提案する書。本書では、公の学校教育や民間の教育事業である塾や予備校などではできない学習支援の必要性や意義、学ぶ楽しさの体験、そして学びを通して世の中を見る目が変化していく教育内容の一端を紹介。現代日本における教育の盲点を埋める貴重な提案が読み取れる。無料塾とは、まさに無料で参加できる学習塾。この体制を支え維持するために集まった学習支援ボランティア(無償)には、JAXA(宇宙航空研究開発機構)を定年退職した研究者、現役のCA、公認心理師、理科教育の専門家、高校や大学の講師、公務員……など。子どもがふだんの生活では親しく接したことがない魅力的な先生方が参加。「甲州無料塾ココロ」として活動してからは2年。学校やいわゆる塾とは異なる、学ぶこと本来の姿勢に立ち返った「ワクワクするような学習の場」を子どもたちと一体で体験しつつ、これからの人間教育を踏まえた画期的な取り組みの一端が本書で示されている。著者は、西田隆男(代表、公認心理師)、藪内志津子(自由の森学園中学高校非常勤講師)、伊藤賢典(東京電機大学理工学部非常勤教員)、西田みどり(文学博士、芝浦工業大学非常勤講師)。
|
◎著者紹介
甲州無料塾ココロ:西田隆男・ニシダタカオ(甲州無料塾ココロ代表、公認心理師、学校心理士スーパーバイザー、自由の森学園中学高校スクールカウンセラー、NPO法人埼玉ダルク理事長)/藪内志津子・ヤブウチシヅコ(自由の森学園中学高校非常勤講師:英語)/伊藤賢典・イトウケンテン(自由の森学園中学高校非常勤講師:理科、東京電機大学理工学部非常勤教員:理科教育)/西田みどり・ニシダミドリ(文学博士、芝浦工業大学非常勤講師、大正大学非常勤講師)
目次
はじめに―― 「ワクワクする学びの場」を目指して
第1章 学習支援ボランティア事業の現状と課題──民間運営の無料塾から見えてきたこと
1.はじめに
2.学習支援ボランティア事業を支える二つの法律
3.学習支援ボランティア事業の現状
(1)自治体の教育委員会主催
(2)自治体が民間のNPO法人に委託
(3)民間が独自に運営
4.民間による「甲州無料塾ココロ」のケース
(1)甲府市の県立図書館交流ルーム教室
(2)山梨市の社会的養護施設・自立援助ホームLively朋教室
(3)埼玉県飯能市の中央地区行政センター
5.学習支援ボランティア事業の課題
コラム:「できること」「したいこと」に働きかける教育を
6.新しい学び方の必要
7.まとめ
コラム:「大切に育てられている」という感覚
第2章 豊かな生き方につながる英語学習──自立した学習者(Self Organized Learners)の育成に向けて
1.はじめに
2.言葉の力
3.言葉と文化
(1)映画
(2)ファンタジー
(3)絵本
コラム:マインドセットを変えれば、望んでいるような変化が訪れる
(4)歌
(5)モダンメディア
4.メッセージ
(1)「七世代先の子どもたちへ」
(2)「私の国には○○があります」
5.英語を学ぶことから
コラム:学校の「当たり前」は、本当に当たり前?
第3章 「自然から学ぶ」サイエンスの授業
1.はじめに
2.子ども達は、学校で何をどのように学ぶことが大切なのだろうか
3.理科を学ぶ授業から、自然を知り自然から学ぶサイエンスの授業へ
4.物理を学ぶ高校生の君へ「なぜ理科を学ぶのか」
5.理科を学ぶのではなく、理科を通して、自然を学ぶ
6.授業の記録:選択物理Beyond 僕らは、はどうやって地球に引っ張られているんだろう?
コラム:幸福な学びは人間関係から生まれる
7.高校生の授業感想
8.おわりに
コラム:子どもの貧困は人生での選択肢を狭める
第4章 論理的な考え方を身に付けるためのライティング技法
1.はじめに
2.帰納的推論法を活用して論理的に書く
◎帰納法の考え方
◎帰納的推論法で書かれた「幸運な発見を偶然にする方法」の構造分析
3.演繹的推論法を活用して論理的に書く
◎演繹法の考え方
◎演繹的推論法は接続語の連結で書くことができる
◎演繹的展開例文「労働人口減少と自動化技術」
コラム:子どもはみんなそれぞれ違う
4.帰納法と演繹法を合体して論理的文章を書く
◎長い文章を書くときは演繹的推論法と帰納的推論法の両方を使用する
◎演繹的推論法と帰納的推論法を合体した例文
5.まとめ
第5章 「メンタルトレーニング」講座──なぜ、「無料塾」でメンタルトレーニングなのか〈自主的な学習意欲を高めるために〉
はじめに
第1回 メンタルトレーニングの目的
《理論編》
《実践編》
◆効果を高める「フィードバック」技法
第2回 モチベーション(動機付け)を明確にする
・ゴール(目標)の設定―SMART(スマート)
《実践編》
コラム:信頼できる人に囲まれた安全な場が子どもを伸ばす
第3回 リラクセーション
◆技法:自律訓練法
第4回目 マインドフルネス技法
・マインドフルネス(mindfulness)とは
◆マインドフルネス技法のやり方
第5回 レジリエンス・トレーニング(1)
・レジリエンスとは
◆レジリエンス能力の原則と応用
第6回 レジリエンス・トレーニング(2)
◆7つのレジリエンス・スキル
コラム:不登校は教育システムの中の「炭鉱のカナリヤ」
第7回 アファメーション
(1)アファメーション(affirmation)とは
(2)3つの基本原則
(3)5段階のプロセス
(4)核(コア)となるセルフトークを考える
第8回 ブレインジム
(1)ブレインジム―教育キネシオロジー
(2)身体の3つの次元
(3)アクション・バランス―PACE(ペース)
(4)主なエクササイズ
第9回 東洋式自己整体
◆操体法(そうたいほう)
第10回 RAS(網様体賦活系)の活用
(1)RAS(ラス)の働き
(2)RASの特徴
(3)RASの活用法
(4)ネガティブ感情の対処法
コラム:自学自習する習慣
おわりに
はじめに――「ワクワクする学びの場」を目指して
いま日本では、経済格差、そして教育格差が問題になっています。このような社会的格差は私たちの幸福に悪影響を与えることが科学的研究から明らかになっています。イギリスの経済学者リチャード・ウィルキンソンが経済格差と幸福度について行った調査によると、幸福度とGDP(国内総生産)の間には有意な関係は見られず、幸福度を左右しているのは国内での経済格差だという結果が出たそうです。つまりGDPの高い国が幸福度が高いのではなく、GDPが高くなくても格差の少ない国のほうが幸福度が高い、人々は幸福に暮らしているということです。
日本はすでに格差社会になっており、貧困状態に置かれた子どもは6人に1人です。格差はただお金がないというだけでなく、教育環境に影響を与えます。親が生活に手いっぱいで子どもの教育に無関心であったり、塾に行きたくても親に言いだせない、家に一冊の本もない家庭もあります。あるいは、格差の中で学校という集団生活になじめず、不登校になる子どももいます。学校現場で一人一人の子どもが置かれた状況を把握するのは容易ではありません。毎日のように報道される子どもや教育機関を巡る事件からもそれは明白です。
子どもの教育は健全な社会を構築する土台です。それがいま十全に機能していない。この教育的危機に対して、私たちはどのようなことができるでしょうか。地域で生活する子どもの実状にあったやり方で、なにができるだろうか。
この課題に対する対処法のひとつとして思いついたのが、地域に根差した「学習支援ボランティア・無料塾」です。私たちの無料塾は、公の学校教育や民間の教育事業である塾や予備校などではできていない学習支援を行うことを目標としています。それは偏差値という指標に捉われない学習支援であり、学ぶ楽しさを体験し、学びを通して世の中を見る目が変化していくことを実感できるような、そんな学習支援です。
それが可能なのは、集まった学習支援ボランティアの多彩さに依拠しています。JAXA(宇宙航空研究開発機構)を定年退職した研究者、現役のCA、公認心理師、理科教育の専門家、高校や大学の講師、公務員‥‥など、子どもがふだんの生活ではあまり親しく接したことのない大人が、仕事の合間を縫って無償で参加してくれています。
世の中には、ボランティアだからこそ可能なことがあります。例えば、世界中で発生している大災害の支援活動にはたくさんのボランティアが集まります。そこで被災者とのフラットなコミュニケーションが始まります。<助ける人 対 援助してもらう人>という一種の縦の関係ではなく、隣人同士のような助け合いです。スーパーボランティアと呼ばれる尾鼻春夫さんは、そんなボランティアがどれほど社会に対して貢献できるかを示してくれました。同じことが恐らく教育分野にも当てはまると思います。尾鼻さんのボランティアスピリットが世間に知られるまでに15年かかっています。甲州無料塾ココロは活動を始めてまだ2年です。学校や塾とは異なる、学ぶこと本来の姿勢に立ち返った「ワクワクするような学習の場」を、子どもたちと一緒につくっていきたいと念願しています。
甲州無料塾ココロ代表 西田隆男
TOPに戻る